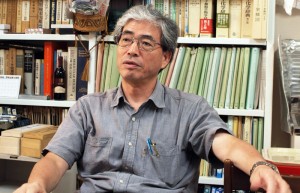「℃」をめぐる魚と研究者のものがたり 渡部終五

深くて冷たい海の底、熱帯雨林を流れる河川、公園の池。水のあるところには、かならずといっていいほど魚が棲 んでいる。魚類は、外の気温によって体温が変化する変温動物。およそ-2℃から30℃という大きな温度差が生じる水の中で、彼らはどのように生活しているのだろうか。
変温動物 だからこそおもしろい
 「ごく普通に見かけるコイだけど、実はとてもおもしろい生き物でね…」と、 渡部さんは口火を切った。
「ごく普通に見かけるコイだけど、実はとてもおもしろい生き物でね…」と、 渡部さんは口火を切った。これから冬にかけて、池の水温が徐々に下がっていく中、コイの体内では筋肉の構造が劇的に変化するという。魚の筋肉は、私たちが 普段食べている魚肉のほとんどを占める部分。その筋肉の主成分であるミオシンは、ATPaseという酵素を使ってATPを分解し、その時に発生するエネルギーで筋肉を動かしている。魚が体を左右に揺らして水の中を自由自在に泳ぐことができるのも、このエネルギーがあるからだ。ATPaseの活性が高いほど効率よく筋肉を動かすことができるが、低温になるとATPaseの活性が下がり、筋肉が動きにくくなる。渡部さんは大学院生の協力を得て、コイのミオシンは低温になると一次構造が変化し、ATPase活性を高いまま維持することができることを発見した。興味深いのは、この温度依存型のミオシンがコイやキンギョなどのごく限られた魚のみに見られるという点である。実は、海や川で生息する魚は、水温が低くなると暖かい場所を探し求めて移動できるのだが、コイの ように池や湖など閉鎖的な空間で生きる魚には逃げ場がほとんどない。そのため、温度変化に耐えられるよう体内の機能を進化させてきたのだろう。身近な生き物として知られているコイだが、変温動物の中でも特におもしろい特徴を持っていたのだ。
5℃の違いで鮮度が倍増?!
 そんな研究を続けていたころ、魚の死後硬直 に関する研究依頼がきた。釣り上げた魚は、0℃の氷水に浸すことがよいと考えられがちだが、これは死後硬直を早めることになる。実は、この死後硬直が起こ る直前が、最も鮮度が高い状態なのだ。そして昔から、マダイやヒラメなどの魚は、5℃から10℃という温度が最も鮮度を長く保つことができることが知られ ている。死後硬直が始まる時間と温度のひみつには、筋肉が関わっているのではないか。そう考えた渡部さんは、大学院生と一緒に死後硬直が起こる前後の筋肉の変化を調べた。10℃に比べて0℃のほうが筋肉にある筋小胞体でカルシウムが吸収されず、筋肉内にカルシウムが溜まるようになる。すると、ATPase 活性が高くなりATPがどんどん筋肉に使われて硬直が早く進んでしまうことが分かった。その後、魚が棲む環境の温度と貯蔵温度の差が少ないほど鮮度が保たれるという事実も明らかになった。「死後硬直には筋肉が大きく関係してくる。筋肉の研究をやってきたからこそ解明できたことだ。これを応用すれば、魚ごとに最適な温度を見つけられるし、適度な運動をさせることで魚の筋肉を改造すれば、鮮度を長く保つことができるかもしれない」と、渡部さんは話す。
そんな研究を続けていたころ、魚の死後硬直 に関する研究依頼がきた。釣り上げた魚は、0℃の氷水に浸すことがよいと考えられがちだが、これは死後硬直を早めることになる。実は、この死後硬直が起こ る直前が、最も鮮度が高い状態なのだ。そして昔から、マダイやヒラメなどの魚は、5℃から10℃という温度が最も鮮度を長く保つことができることが知られ ている。死後硬直が始まる時間と温度のひみつには、筋肉が関わっているのではないか。そう考えた渡部さんは、大学院生と一緒に死後硬直が起こる前後の筋肉の変化を調べた。10℃に比べて0℃のほうが筋肉にある筋小胞体でカルシウムが吸収されず、筋肉内にカルシウムが溜まるようになる。すると、ATPase 活性が高くなりATPがどんどん筋肉に使われて硬直が早く進んでしまうことが分かった。その後、魚が棲む環境の温度と貯蔵温度の差が少ないほど鮮度が保たれるという事実も明らかになった。「死後硬直には筋肉が大きく関係してくる。筋肉の研究をやってきたからこそ解明できたことだ。これを応用すれば、魚ごとに最適な温度を見つけられるし、適度な運動をさせることで魚の筋肉を改造すれば、鮮度を長く保つことができるかもしれない」と、渡部さんは話す。博士課程は訓練
 学生時代、 ホタテガイの筋肉タンパク質を作るミオシンの活性について調べているうちに、変温動物である魚の筋肉に見られる「温度馴化」という特別な性質に興味を持ち 始めた。そして、それはやがて遺伝子レベルでの筋肉の違いを知りたいという欲求に変わってきた。現在は、トラフグを使って筋肉の遺伝子について研究中である。博士課程の数年間は、魚の筋肉の性質を知り、様々な実験方法や知識を身につけるための訓練のようなものだったと、渡部さんは言う。そして、ノウハウを積んできた今だからこそ、こうして温度馴化に伴うミオシン構造の変化や遺伝子の解析の研究をすることができるようになったのである。
学生時代、 ホタテガイの筋肉タンパク質を作るミオシンの活性について調べているうちに、変温動物である魚の筋肉に見られる「温度馴化」という特別な性質に興味を持ち 始めた。そして、それはやがて遺伝子レベルでの筋肉の違いを知りたいという欲求に変わってきた。現在は、トラフグを使って筋肉の遺伝子について研究中である。博士課程の数年間は、魚の筋肉の性質を知り、様々な実験方法や知識を身につけるための訓練のようなものだったと、渡部さんは言う。そして、ノウハウを積んできた今だからこそ、こうして温度馴化に伴うミオシン構造の変化や遺伝子の解析の研究をすることができるようになったのである。渡 部さんは、魚を研究する魅力を次のように語る。「本当の研究のおもしろさっていうのは、自然の中にあるたくさんの分からないことを解明していくところにあるんだよ。その中でも私は、生物界の大きな存在であり変温動物という特別な性質を持った魚に興味を持った。こうした研究は、今は100%の自信をもって答えられないが、いずれ何らかの役に立つだろう。それで良いのではないかと思う」。研究の醍醐味をダイレクトに味わえる魚という生き物は、研究者を魅了し続 けていく。
渡部終五
- 東京大学大学院農学生命科学研究科水圏生物科学専攻 教 授
- 1976年、東京大学大学院農学系研究科水産学専門課程修了。
- 1996年より現職。魚類の温度適応に関する分 子生物学的研究、水圏生物を対象にしたタンパク質工学的研究を行っている