音楽やる人必見:誰でも利用できる能動的音楽鑑賞サービス「Songle」が新しい!
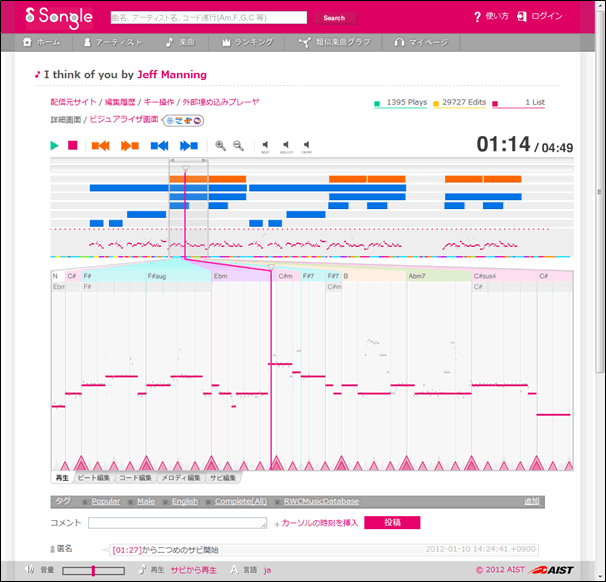
産業技術総合研究所と科学技術振興機構が発表したというのがまた新しい感じがします。Songle。
インターネット上の音楽コンテンツをより能動的で豊かに鑑賞できるサービスというのは、どういうことなのかというと、ネット上に置いてあるmp3音源を解析し、その結果とともに音楽を楽しむことが出来るというもの。
このサービスの狙いは、音楽を理解してもらうという所にある。ただ、聴くのではなく、その楽曲がどうなっているのかを理解して欲しいというものだ。
Songleには三つの特徴がある。
- ウェブ上の楽曲の中身を音楽理解技術で自動解析して「音楽地図」として可視化
- サビ出し機能、コード進行検索機能、外部埋め込みプレーヤー機能による音楽鑑賞
- ユーザーが自動解析の誤りを訂正できるインタフェースを提供
1についてはこうだ。みてもらうのがはやいだろう
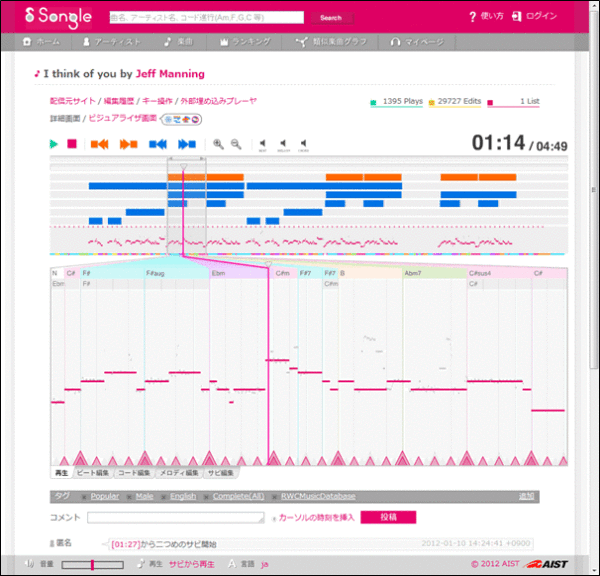
図1 楽曲の中身を自動解析して「音楽地図」として可視化した詳細画面の表示例
「音楽地図」は横軸が時間であり、上部の大局的な表示部には、楽曲中の繰り返し構造を可視化した楽曲構造が表示され、最上段にサビ区間、その下の5段にさまざまな長さの繰り返し区間が表示されている。各段の中で、着色されている区間同士が似ている(繰り返しである)ことを表している。下部の局所的な表示部は、上部で選択した区間の拡大表示である。最下部では、小さい三角形が各拍(四分音符に対応するビート)の位置を、大きい三角形が小節の先頭を示す。そのビート構造の上には、メロディーの歌声の音高がピアノロール注7)状に表示されている。その上には、それぞれのコード名がテキストで表示されている(例えば、コード名Ebmは、根音がEbであり、その構成音を示すコードタイプがmであることを意味する)。
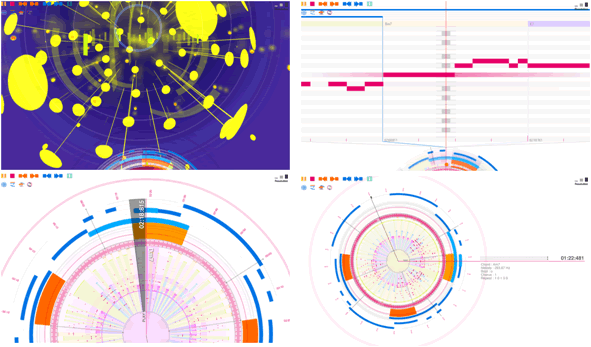
図2 楽曲の進行に合わせて解析結果をアニメーション表示するビジュアライザ画面の表示例
4つの代表的な音楽的要素(楽曲構造、ビート構造、メロディー、コード)に密接に連動して表示内容が動的に変わる。図の左上の幾何学模様が連動して大きく動く表示、右上のピアノロール状の表示、左下の半円状に描かれた音楽的要素の表示、右下の全体を俯瞰した円盤状の表示の4種類の形式を切り替えられる。詳細画面が音楽的要素を把握するためのインタフェースであるのに対し、ビジュアライザ画面は音楽的要素に基づいて動的に生成される表示を楽しんでもらうためのインタフェースとなっている。
音楽地図機能が面白いです。自分でコード進行変更したものを聴くこともできるので、いじることができるのが面白いですね。
埋め込みプレーヤーを貼り付けてみました。こんな感じです
自動解析の結果は、人が聞いた上で訂正することもできるという仕組み。ソーシャルを意識しているし、それはサービスにも現れていて、Twitter等のアカウントでログインすることが可能です。
音楽やる人は良いんじゃないでしょうか。面白いと思いますよ!
(mp3だけじゃなくて、YouTube動画とかにも対応してほしいなあ…)


