理系の海外留学:大学院3年目 Candidacy Examという悪夢
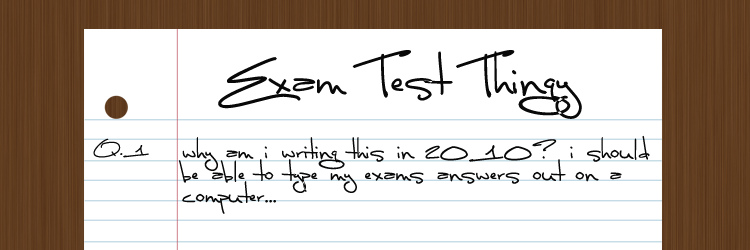
前の記事→ 理系の海外留学:大学院2年目 ティーチングのプレッシャー
アメリカの大学院のPh.D.コースに6年間いて、博士号を取得しました。
所謂、博士一貫コースというもので、修士号を授与されることはありません。
腰を落ち着けて研究をできる素晴らしい環境だったと思いますが、3年目の終わりまでに終了すべき一つの関門があります。
その名もCandidacy Exam。
この試験をパスすると、博士候補生(Ph.D. Candidate)と呼ばれることになり、論文さえ出せばいつでも卒業をできる状態になります。
今日はアメリカでPh.D.を取得した人間が「二度と経験したくない」と口を揃えるこの試験についてのお話。
課題:自分の研究以外のトピックで科研費の申請書を書け
Candidacy Examのお題は「自分の研究以外のトピックで科研費の申請書を書け」というものが多いようです。
自分の指導教授とは異なるオリジナル研究を始めなさい、という大学院側からの明確なメッセージです。
ただ、オリジナルな研究をすぐはじめる予算をとるための業績は大学院生にはないことが殆ど、だから仮想の状態で練習をさせる。
さらには、この試験によって、自分の頭で考えない学生をふるいにかけます。
3年の終わりになると如実に同級生が減っていくんですよね。。。
プロセスとしては以下のように進みます。
1)自身の申請書を審査する審査委員会をつくる
→自分自身で4人の教授に僕の委員会に入ってよ、と頼みます(所謂、博士論文の主査・副査選び)。
2)申請書の概要1枚を送る(計4人の教授へ)
→ここではねられる場合もあり、その場合は指導を受けながら何度かチャレンジ
また、トピック選びに指導教諭は一切アドバイスをしません(これはうちのボスだけだろうか。。。?)
3)10枚の申請書を1ヶ月で作成し、送る
→この中身をガチで審査されます。
一発OK、Major revision、minor rivision、OUTなど評価をされます。
原則2回OUTになると試験に落ちて、プログラムを辞めさせられます。
4)申請書が通ったら1ヶ月以内に口頭試験を受ける
これが悪夢。
2時間何を聞いてもよい試験という地獄
会議室、自分の書いた申請書、ホワイトボード、マーカー、4人の教授、僕。
制限時間2時間内で教授陣は何を聞いてもいいという試験。
死ねます。
この準備のための関連論文を読み漁るわけですよ、準備期間に。
だって何聞かれてもOKなようにしとけって試験なんだから。
今振り返ってみれば質のよいディスカッションを2時間したなという感想なんですが、当時はほんとに死ぬかと思いました。
2時間で聞かれたのは3問、僕の場合は知識が及ばないところまで追い込まれたのち、その中でどういう反応をするかということを試されました。
いや、今思い出しても胃がヒヤッとする。
アメリカの高等教育の凄さ
学生にとっては地獄以外の何者でもないのですが、この試験のすごいところは教授陣が相当の労力を惜しまずに使っているというところです。
申請書をガチで読み込み、アドバイスをするわけですから。
これが制度として成り立っているところが奇跡だなと思うわけです。
もう僕はやったから言えるんだけど、是非日本の博士課程にも導入して欲しいなと思っています。
