魚の腸に棲む小さな活躍者たち 杉田治男
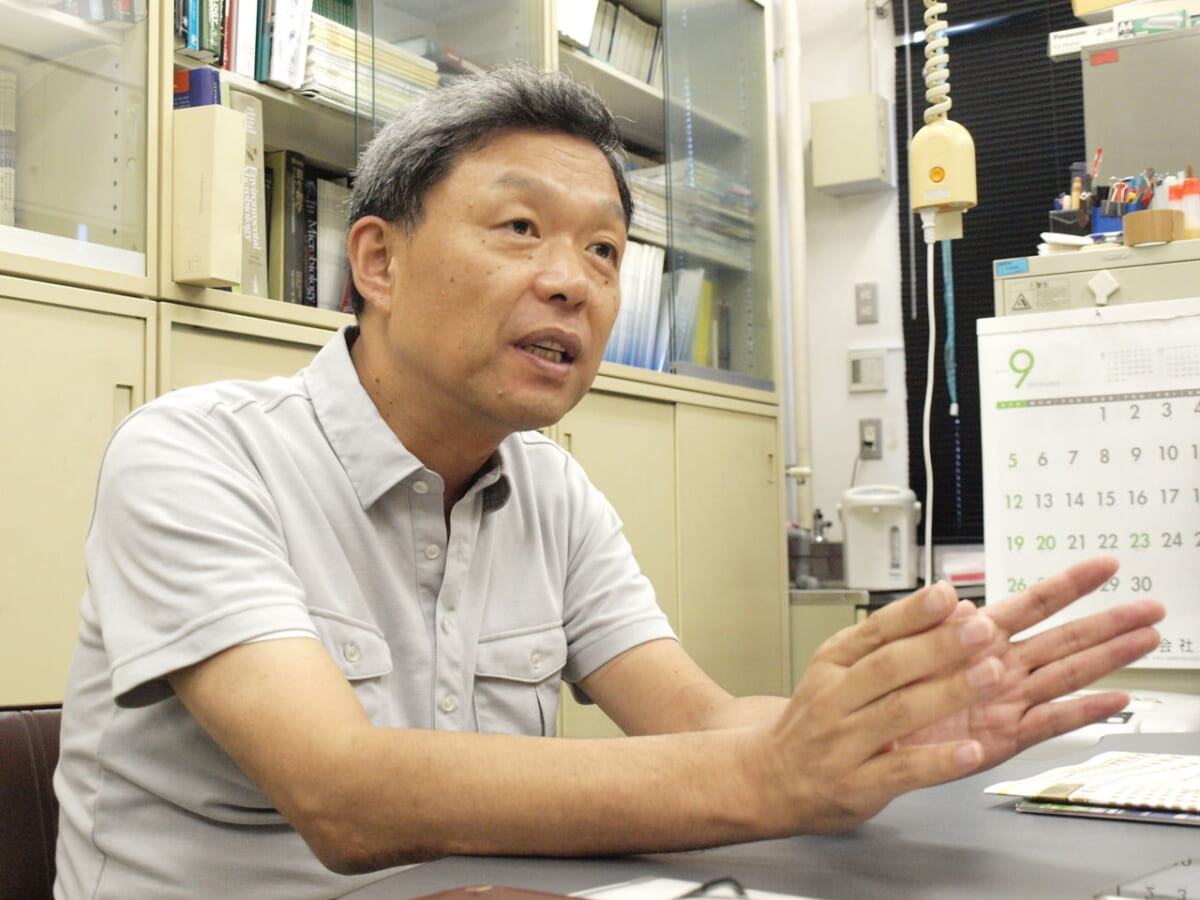
ヨーグルトでおなじみのビフィズス菌や、研究の世界で活躍している大腸菌など、私たちヒトの腸には500種類以上ものいろいろな菌が棲んでいる。魚もまたしかり。水の中に生きる魚は常にえらから水を取り込んでいるが、それは同時に様々な病原菌やウイルスの侵入を許すことになる。そんな魚の腸内には変わったことをする菌がたくさんいると、杉田治男さんは話す。
おなかの中は菌種のるつぼ
魚の腸内環境は、彼らが食べるエサと密接に関わっている。同じエサでもコイやアフリカ原産のティラピアでは成長に影響がでないのに、ウナギやアメリカナマズだと成長不良や食欲不振に陥る。このことを疑問に感じた杉田さんは、これらを含む6種類の魚の腸内細菌を調べてみたところ、コイやニジマスの腸内には偏性嫌気性細菌が多く棲み、ビタミンB12を大量に分泌していたことを突き止めた。実は、魚は偏性嫌気性細菌に栄養を与える代わりに、ビタミンB12をもらうという共存関係を作り上げていたのである。一般的には、酸素が溶けている量やエサの種類に依存して腸の長さが変わるため、そこに棲む細菌の種類も変わってくるのだが、なぜコイやティラピアにはこうした菌が共存しているかについては、まだ分かっていない。他にも、不飽和脂肪酸の一種であるEPAを生産して魚に供給したり、消化を助ける酵素を分泌する菌もいる。そしてなんと、抗菌物質を分泌して外からやってくる病原菌やウイルスを倒す役目を果たす菌もいるというのだ。長い進化の過程で、魚は腸内細菌と多種多様な共存関係を築きあげてきたのである。
腸内細菌が挑む世界の課題
こうした微生物の研究は、養殖の分野に活かされているという。2050年には食糧の確保が大きな課題となる地球では、養殖技術に注目が集まっている。現在、養殖技術が直面する問題のひとつに、エサと抗生物質の投下による水質汚染がある。水槽の中では、日和見感染症などの病気やストレスが誘発されやすく、抗生物質を大量に投下して感染症を治療することが求められる。さらに、魚はこうした化学物質を体内に蓄積してしまうため、魚を食べる私たちにとってもリスクが高い。こうした問題に対して杉田さんは、腸内細菌を利用しようと考えている。腸内細菌を使い分けることで、養殖に欠かせない衛生管理という仕事を、水槽の中でなく魚の腸内で行おうというのだ。空間的な制約とコスト面の問題を大きく解決できる画期的なアイデアである。「あまり知られていないことなのですが、世界で食べられている魚の1/3が養殖なのですよ。養殖モノは美味しくないというイメージがありますが、そうではありません。養殖という技術には可能性が秘められています。私は腸内細菌を使ってその可能性を探っていきたい」と、杉田さんは語ってくれた。先見の明を持った研究者に見初められた腸内細菌は、いま人類に課された食糧問題に立ち向かおうとしている。
魚の研究はアイデアを試すステージ
 実は、高校生の時から養殖をやりたいと考えていた杉田さんは、養殖コースのある日本大学に迷わず進学。そこで、魚の腸内細菌に関する研究分野が未開拓であることを知った。もしかしたら自分はこの分野の第一人者になれるかも!そう考え、養殖に活かすことができる微生物学の道へ進んだという。魚の腸内細菌は知られていることはほとんどなく、菌の分類も90年代に入ってからやっと行われるようになったほど。現在もなおその全体像がつかめていないそうだ。「この分野には、自分のアイデアをためすためのテーマがたくさん転がっている。それをひとつひとつ試してきたし、アイデアが当たったときはすごくうれしいんです」と、杉田さんはいう。今後は、魚のエサであるワムシなどにも注目していくのだそう。魚の腸内環境の浄化に必要な菌を、エサと共に摂取することができれば、水槽浄化の機能も高まるはずだ。
実は、高校生の時から養殖をやりたいと考えていた杉田さんは、養殖コースのある日本大学に迷わず進学。そこで、魚の腸内細菌に関する研究分野が未開拓であることを知った。もしかしたら自分はこの分野の第一人者になれるかも!そう考え、養殖に活かすことができる微生物学の道へ進んだという。魚の腸内細菌は知られていることはほとんどなく、菌の分類も90年代に入ってからやっと行われるようになったほど。現在もなおその全体像がつかめていないそうだ。「この分野には、自分のアイデアをためすためのテーマがたくさん転がっている。それをひとつひとつ試してきたし、アイデアが当たったときはすごくうれしいんです」と、杉田さんはいう。今後は、魚のエサであるワムシなどにも注目していくのだそう。魚の腸内環境の浄化に必要な菌を、エサと共に摂取することができれば、水槽浄化の機能も高まるはずだ。
秋も深まり、黒潮に乗って今年もたくさんの魚が日本近海にやってくる。釣りや魚屋さんでまるごと一匹の魚を見かけたら、彼らを手にとってみよう。そのお腹の中で細長く折り畳まれた腸を顕微鏡でのぞけば、たくさんの小さな活躍者たちと出会うことができるだろう。
杉田治男
- 日本大学 生物資源科学部海洋生物資源科学科教授
- 1980年、京都大学大学院農学研究科修了。農学博士。
- 1999年より現職、海洋微生物及び魚類の腸内細菌を用いた浄化システムの研究を行っている。

