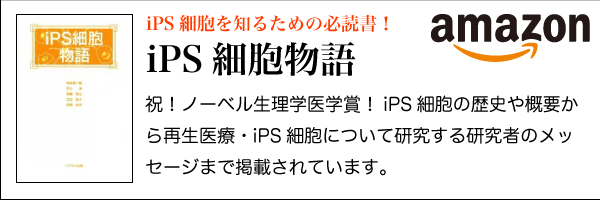再生医療技術の新しい局面

皮ふなどの細胞から作ることができ、どんな細胞にも変化できる能力をもつiPS細胞は、未来の再生医療の切り札として期待され、研究が進められています。
たとえば肝臓が悪くなってしまった患者の皮ふからiPS細胞を作り、体外で培養したあとで肝細胞に変化させて身体に戻すことで、他人の組織を使う通常の移植医療では避けて通れない拒絶反応を起こさずに治療できると考えられているのです。
ところが2011年5月13日、カリフォルニア州立大学サンディエゴ校のYang Xuらは、自分の体から作ったiPS細胞でも拒絶反応が起こりうるという実験結果を示しました。
もともと拒絶反応は、体を外敵から守る免疫システムが、移植された細胞を「これは自分の体ではない」と判断、攻撃することによって起こります。
このしくみは私たちが胎児のころ、体の中で作られる様々なタンパク質が免疫システムに渡され、「その期間に提示されたタンパク質は自分の体の部品である」と覚えることで、作られています(専門用語で免疫寛容といいます)。
Xuの研究では、本来、発生段階の一時期のみにしか作られないタンパク質が、iPS化する過程の中でまた作られるようになってしまうことを発見しました。
特にZg16とHormad1という2つのタンパク質は、免疫寛容の期間にも体内で作られていないため、免疫システムに「自分の部品だ」と認識されません。
それがiPS細胞になると作られるようになり、自分の体由来の細胞にも関わらず、「自分のものではないタンパク質を持っている」=攻撃対象として認識されてしまったのです。
しかしながら、これでiPS細胞が再生医療に使えないかというとそういうわけではありません。
このような研究成果を踏まえながらきちんと安全性を評価していくことで、より確実な医療技術へと発展していくのです。