日本発の太陽光パネル掃除ロボット、中東へ 三宅 徹
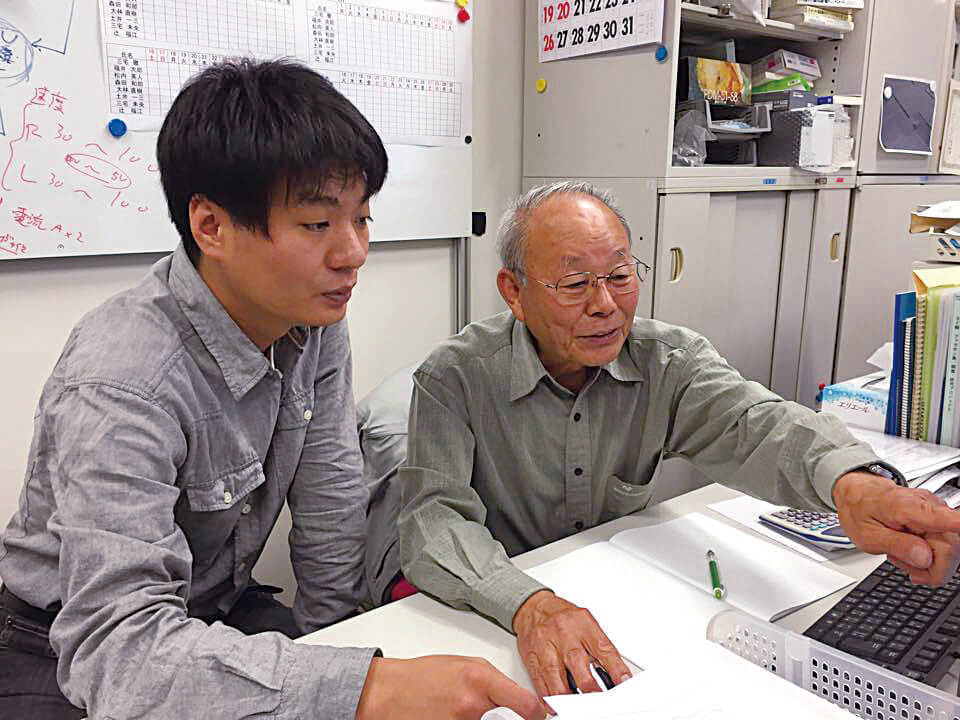
ここ10年間、大学発ベンチャーの多くは廃業に追い込まれ、生き残った企業も多くが飛躍を果たせずにくすぶっている。そんな中で工学分野の博士号を持つ三宅さんは、学生時代に香川大学発ベンチャーの株式会社未来機械を自己資金のみで設立した。設立から10年という年月をかけて基盤を固めて、今、個人経営からグローバル企業へと一気に成長しようとしている。日本の強みであるロボット技術を活用して開発した太陽光パネルの掃除ロボットが、中東で注目を集めている。
欧米でもアジアでもなく、中東へ
REN21 が発行する「自然エネルギー世界白書2014」によると、太陽光発電の累計導入量は年々指数関数的に増加し、2014年に約1億8,000万kWに達しようとしている。
国別ではドイツが約3,800万kW、中国が約2,800万kW、日本が約2,200万kW(推計値)、その後アメリカとイタリアが続く状況だ。
 そんな中で未来機械が狙うのは、市場としては先進国に比べてまだまだ小さいが、今後の飛躍的な成長が期待される中東市場。
そんな中で未来機械が狙うのは、市場としては先進国に比べてまだまだ小さいが、今後の飛躍的な成長が期待される中東市場。
中東では砂漠の影響で太陽光パネルは掃除をしないと大量の砂が表面に付着し、発電効率が低下する。1ヶ月掃除をしないと、40%程度も発電量は低下してしまうという。
そのため中東では、定期的に人力で太陽光パネルの清掃を行っているが、気温40度以上の灼熱の日射のために清掃自体も大変な仕事になっているのだ。元々窓拭きロボットの開発をしていた未来機械は、その機構を太陽光パネル掃除ロボットに活かせないかと市場ニーズを探っていた。
2008年頃には実際にアメリカにも視察に行ったものの、ニーズがないことがわかり諦めかけていた。
そんな中で2011年、知り合いから紹介を受けた太陽電池メーカーにロボットを見せたところ、中東ならばニーズがあると紹介され本格的な開発がスタートした。
水を使わずに自走するロボット
 未来機械の開発した清掃ロボットは、太陽光パネルを自動で掃除する自走式ロボットだ。8つの超音波センサでパネルの端を認識し、自動で向きを変えて掃除を進めていく。一番の特徴は、清掃に水を使わずにロボットの前後についたブラシで砂を落とす点にある。中東において水がとても貴重な資源であることを知っているからこそ取り入れた機能だ。一回の駆動時間は2時間で、アレイ(数十枚から数百枚のパネルの塊)間の移動は人が載せ替え、その際にバッテリーも交換するのだという。バッテリーの駆動時間を延ばすために、バッテリーを大きくするとロボットの重量が増加してしまうし、すべて自動で掃除ができる仕様だとコスト面で採算が取れず、利便性が下がるという理由からだ。2014年にプロトタイプ3台を中東に納品し、現在は量産に向けた準備も進んでいる。
未来機械の開発した清掃ロボットは、太陽光パネルを自動で掃除する自走式ロボットだ。8つの超音波センサでパネルの端を認識し、自動で向きを変えて掃除を進めていく。一番の特徴は、清掃に水を使わずにロボットの前後についたブラシで砂を落とす点にある。中東において水がとても貴重な資源であることを知っているからこそ取り入れた機能だ。一回の駆動時間は2時間で、アレイ(数十枚から数百枚のパネルの塊)間の移動は人が載せ替え、その際にバッテリーも交換するのだという。バッテリーの駆動時間を延ばすために、バッテリーを大きくするとロボットの重量が増加してしまうし、すべて自動で掃除ができる仕様だとコスト面で採算が取れず、利便性が下がるという理由からだ。2014年にプロトタイプ3台を中東に納品し、現在は量産に向けた準備も進んでいる。
世の中に存在しないロボットを生み出す
未来機械が強みとするのは移動機構だ。移動機構の開発だけでなく、課題の解決に必要なセンサの開発や基板設計、組込システムや駆動系の開発、耐久性試験までを自社で担える強みも持っている。「今まで見たことも聞いたこともないロボットを生み出すことは、新しい生き物を生み出すようなもの。それには、世界中の要素技術を知っている必要があり、素材と制御系も知ってなきゃいけない。そこから新しい機構を生み出し、さらに十分な耐久性と事業化できるコストを実現するよう、シンプルなものに絞り込むんです」と三宅さんは語る。「従来のロボットは、求められる機能に対して、無駄なものが多い。完全な自動化ありき、では無駄な機能をのせてしまう。人との分担ありきで考え、人が得意なこと、できないこと、とのバランスを考えないと意味がない」。10年間で様々な受託開発と自社開発を行ってきた経験が言葉に重みをもたせる。
若手研究者と百戦錬磨のエンジニアがタッグを組んで世界を目指す
現在、同社のスタッフは8名。ユニークなのは、三宅さんを含め、博士号を持つ研究者2名を筆頭に機械、電気電子、材料など大学で最先端の研究を行ってきた平均年齢32歳の若手人材4名と、数十年間ゼロからものづくりに携わてきた経験を持つ平均年齢60歳のベテラン、シニア人材4名で研究開発を進めている点だ。
「最先端のセンサや制御系を組み込むだけでは、本当の意味で現場で使えるロボットを開発することはできません。ものづくりの濃密なノウハウを持ったシニア人材とタッグを組むことで、今までにない価値を生み出すことができるんです。うちの会社はベテラン・シニアが一番元気で、一番熱い」。センサーをはじめ、日進月歩で進歩する技術は若手がキャッチアップし、素材や機構の工夫は数多くの経験と知識を持つベテラン・シニアが中心となる。現在、少しずつロボットベンチャーは増加傾向にあるが、ものづくり分野において未来機械ほど研究者とシニア人材が融合している事例は珍しい。日本のロボットベンチャーが世界で戦えるヒントがここにある。(長谷川 和宏)
