〔リバネスセンシズ〕変革する教育を先導するリーダー(前編)
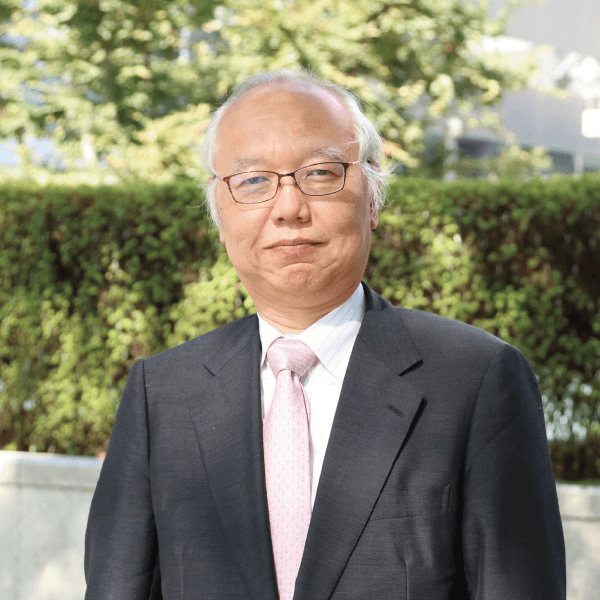
リバネスセンシズでは、リバネスメンバーのインタビューを通して、そのパッションを紐解き、実現しようとする個々の未来像をお伝えします。
森安 康雄(もりやす やすお)
(聴き手:佐野 卓郎)
森安 康雄(もりやす やすお)さんは、初の「第三新卒」としてリバネスに加わったひとだ。以前は、株式会社ベネッセホールディングス(以下、ベネッセ)にてデジタル教育事業開発関連業務などに従事していた。大手企業で活躍していた森安さんが、なぜリバネスのようなベンチャーに参加することになったのか、話を聞いてみた。
佐野:森安さんは、リバネスをどこで知ったんですか?
森安:実は、東京工業大学で行われたバイオコンテスト2006で丸さんに会ったのが最初です。そこでリバネスを知りました。丸さんと会って「変わった若者だなぁ」と思いましたね。そのときは、何か一緒にできたらいいねと話していましたけど、実際に動き出したのは、数年後。コンテストで優勝したDNAカードゲームをリバネスが商品化する頃でした。
「宇宙のプロジェクトを始めるんですけど」って、丸さんから聞いて。
面白そうだから一緒に始めてみたんです。
佐野:「宇宙教育プロジェクト」ですね。シロイヌナズナの種子をスペースシャトルを使って国際宇宙ステーション(ISS)に打ち上げて、1年近く保管した後、全国の子供たちの手で育てるプロジェクトでした。
ベネッセ社内での評判はどうでしたか?
森安:私はもともと「なぜこんなことやるんだ」って言われるような、変わったことをやるのが好きだったので、会社にはおそらく、「また森安がいつもの変なことをはじめた」と思われていたでしょうね。でもみんな、決して嫌ではなかったと思いますよ。メンバーのひとりが、学生時代に宇宙の研究をしていたことを知りました。目を輝かせてくれたのを今でも覚えています。
ただ、プロジェクト実施を決めた後、私自身は別の仕事にアサインされてしまったので、実際に苦労したのは、当時の部下の人たちなんですけどね(笑)。
佐野:宇宙教育プロジェクトって、大企業が扱うビジネスとしては、まったく合理的でないと思うんですが。
森安:そのとおりです。ただ当時は会社としても、教科とは違った部分で、お客様との接点をどうつくるかという課題があったので、このプロジェクトがうまくマッチした部分はありました。
ベネッセは教育・家庭学習という事業領域ではトップランナーです。その人たちがやらなければいけないことは、単に受講者の成績をあげて良い大学に入学させることだけではないんです。ベネッセの仲間もみんながそう考えていたと思います。
じゃあ、その価値を如何にして創り出していくのか。私は運良く、それを常に考え続けるような仕事をさせてもらいました。
例えば、世界で活躍する研究者を招へいして、最先端を担う研究者が何を考えているのか、ワークショップなどで子供たちに伝える取り組みをやったんです。それが子供の将来にどんな影響を与えていくのか、因果関係なんて証明できないわけですが、でもなんか価値があるとみんな思っているんです。だから、会社としても実施したんだと思います。
中学生のためにノーベル賞受賞者の講演会をやったときもそうでした。受講者の目がキラキラとしていて。現場にいて、きっと子供たちに大きなインパクトがあると確信しました。こういう場を提供できることは企業にとっても大切なことだと思いました。
佐野:ちょっと難しい質問ですが、21世紀に入って、企業の在り方も変わってきているのかもしれませんが、今後の社会において企業はどうあるべきだと思いますか?
森安:企業がどうあるべきかは、これから多くの経営者が考えていくと思いますが、確かに難しい質問ですね。正直わかりません。
ただ、その企業で働くひとたちがどうあるべきかについては、色々と考えています。
これまでは、25歳まで勉強して、65歳まではたらいて、あとはゆったりとリタイアという決まったライフスタイルがありました。そしてそれを支えてきたのが企業の存在です。しかし、人生100年という時代に入り、企業よりもむしろ「人」が変わってきていると思います。定年後の長い時間を一体どう過ごすのか。
今後、こうした環境の変化に対応していく人を育て、生み出していく必要があるでしょう。学び直しとか、生涯学び続けるとか、教育の会社には大切なことですよね。って、勝手に言ってるだけにならないように、私自身も現在、色々実践しています。大学院にも行ってますし(笑)。
森安さんは「生涯学び続ける」ことを自身も実践し、現在、東京理科大学大学院MOT専攻に在学している。学びを追求する森安さんが目指すビジョンとはどのようなものなのか。続きは後編にて。
